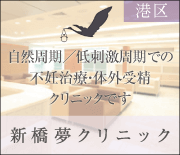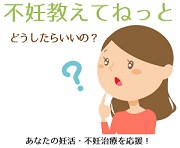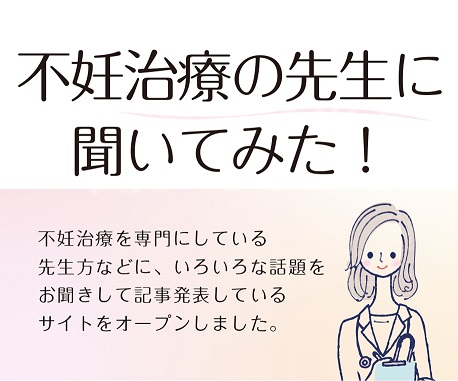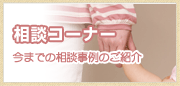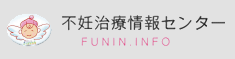人工授精(AID)
病院選び
限られる実施施設とその歴史、親子関係と倫理観。真実を知る権利含め、難しい問題を含む治療の1つです。
夫以外の第三者の精子提供による妊娠。実施施設の件数が少ないのはなぜでしょう。
夫以外の精子でしか妊娠できない時
夫婦の心理と生まれてくる子の福祉
AIDは1949年8月、慶応大学での第1児誕生から50年以上に渡って続けられてきました。
最近では、年間160人余りが出生し、実父を知らない子どもたちは1万人以上に達しました。
AIDを受ける夫婦は、夫の無精子症が主な原因ですが、現在、精巣上体や精巣内から直接精子を回収する方法による顕微授精などが行なえるようになり、その数は減少傾向にあります。
精子提供者は、各病院やクリニックごとで変わってきますが、その選別は生まれてくる子どもと夫婦に矛盾が生じないように、血液型(ABOやRh)を合わせ、遺伝性欠陥、肝炎、性病、エイズなどの検査をして、 安全で妊娠させる能力が十分にある精液であるかどうかをチェックしますが、解決すべき問題も残されている様です。
AIDにより生まれてきた子どもは、夫婦の実子であり、これを揺るがすことなく『何があっても私たちの子ども』と養育し続けるだけの強い信念が必要です。
特に夫は、微妙な心境でしょう。十分な話合いを持って臨むべき治療です。
非配偶者間人工授精(AID)とは
AIDの方法は、ドナー(精子提供者)の精子を使用すること以外、AIHと方法はなんらかわりがありません。
★AIDを受けられる夫婦★
精子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦
夫に精子提供を受ける医学的理由があり、かつ妻に明らかな不妊原因がないか、あるいは治療可能である場合。
(ただし自然閉経の平均年齢である50歳ぐらいを目安とし、それを超えて妊娠できない場合には、「加齢により妊娠できない」とみなし治療を受けることはできない)
★精子提供者の条件★
感染症(肝炎,AIDSを含む性病等)、血液型、精液検査を予め行ない、感染症のないこと、精液所見が正常であることの確認。また、自分の2親等以内の家族、および自分自身に遺伝性疾患がないこと。
★提供者と提供精子の管理★
提供者の感染症検査は、少なくとも年1回施行する。提供者の同意書、および検査結果は少なくとも提供期間中は保存しておく。同一の精子提供者からの出生児数を考慮し、精子提供の期間を2年以内とする。余剰精液を凍結する場合、その保存期間は2年以内とする。
※2003年4月、厚生科学審議会生殖補助医療部会の「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」より
遺伝子的父親の存在
AIDを選択した多くの夫婦は、「できれば子どもに告知したくない」と答えています。またAIDを選択する際に医師から「子どもには告知しないように」と告げられるケースもあるようです。また精子提供者と夫婦がお互いを知ることはなく、生まれてきた子どもについて精子提供者が何の義務も権利も持つことはなく、また生まれてきた子どもが遺伝子上の父親を探すこともできません。
厚生労働省研究班の調査により、精子を提供した人(ドナー)の2/3が「子供が自分に会いに来る可能性を言われたら、提供しなかった」と考え、「提供は匿名のままが良い」が90%近くに上ることが分かっています。
「子供の出自を知る権利」は守られなければならないとする考えが世界的な傾向としてあり、日本でも2003年の厚生労働省の生殖補助医療部会では、15歳以上の子供には「自らの出自を知る権利」を認め、希望があれば遺伝上の父親の氏名や住所を知らせるべきである、と報告書にはまとめています。しかし法整備はなされていないまま。
子どもが欲しいと願う夫婦に、医師は医療を提供する。それは一代限りで終わる問題ではないということまでを説明してくれるドクターがいて、子育てにも啓発的なら much better!!
DR.メッセージ
最終手段としての人工授精
セントマザー産婦人科
人工授精でも、夫以外の精子を子宮腔内に注入するのがAID(非配偶者間人工授精)です。AIHの場合は精液中に精子がいるか、数は少なくても運動性が良好で、自然受精可能であることが条件です。
夫に全く精子のみられない無精子症などで、特に夫婦の希望があれば、AIDを行なうことになります。
また、AIH、AIDのいずれも卵管を利用した不妊治療ですので、子宮卵管造影検査で卵管の通過性があることも必須の条件です。
AIDの適応となる無精子症は、睾丸で精子が全く作られない高度な造精機能障害があるものですが、造精機能障害があっても、睾丸組織から精子細胞を手術的に採取(TESE)し、後期精子細胞を使って顕微授精を行なうことも可能ですし、当院でも積極的に実施しています。それらを試みてもなお妊娠不可能な方はやむを得ずAIDを選択されることになります。
AIDは他人の精子を使うので、提供者のプライバシーや子供の出自を知る権利など、さまざまな問題を抱えることになるので最終手段と考えた方が良いと思います。
患者の声
どうしても自分のお腹で!
結婚して10年目、不妊治療をはじめて4年になります。不妊原因は私になく、主人が無精子性と診断されTESEによる顕微授精を2回しました。1度目は胚移植まで順調でしたが、妊娠しませんでした。
2回目は受精さえせず…。先日の病理検査で精子のもとの細胞もみつけられず、AIDを勧められました。
私は、自分のお腹で夫の遺伝子を持つ赤ちゃんを育てたい。…夫はどうなのか。話し合いの糸口がみつからない状態です。
(福岡県・34歳)
妻に切り出され返事ができない
妻は現在36歳。4年間、不妊治療を受けてきました。原因は私の無精子性なのですが、先日AIDをしてみたいと切り出されました。女性として生まれ、赤ちゃんを産んで育てたいという妻の気持ち、今までの治療のことを思うと踏み切ろうとも思うのですが、生まれてきた子に愛情が持てるか、自分の子として育てていけるか、その自信が持てないのです。私も妻も若い訳ではなく、もっと話し合わなければと思いますが…。
(山梨県・42歳)