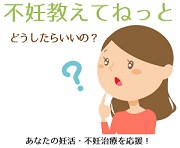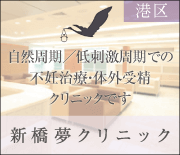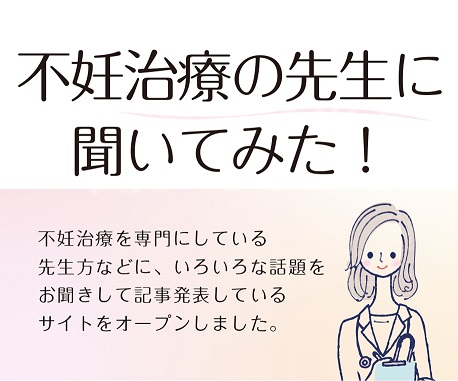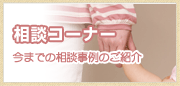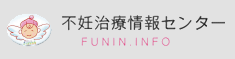夫婦での診療
病院選び
『子どもが欲しいのになかなかできない』
この事実に女性は、まず自分から受診をしてみようという気持ちになることが多いでしょう。
ところが昨今の男性不妊の割合は多く、また、不妊でなくても精子の質が妊娠経過や子どもの人生にも大きく関係します。
夫婦がともに診療を受けるということは、夫婦がともに支えあい、協力して生活をしていけるというひとつの指針ともなります。
ところが、子供が欲しい思いや不妊治療に対する考え方が違い、その思いの差が大きい場合には、治療を巡ってのトラブルも絶えません。夫婦だけで考え方の違いを埋めようとするのではなく、公的機関や治療施設などで行なわれる不妊教室や相談会に同行し、同じように悩むご夫婦が他にもいることを知り、そこから自分たち夫婦のお互いの気持ちを十分に確かめ合い、考え方の違いはあってもお互いが歩み寄れるよう、情報収集や外からの働きかけにも頼るようにしてみましょう。
夫婦の気持ちにズレがあるまま治療を開始すると、一つひとつの検査や治療などが思うように進まないというトラブルが出てきます。
妻だけが診療を受け、夫が治療を受けている施設も主治医の顔もよく知らない状況では、その後の結婚生活や将来の子育ても心配になってきます。
夫婦が揃って治療を受けるからこそ、治療の方針も立てやすく、方法もみつかりやすくなります。初診時から夫婦診療を推進し、治療しやすい環境を整えることも治療施設にとっては大事な治療の一環とも言えるでしょう。
以前よりは、夫婦で診療を受けるケースも多くなりましたが、医師や看護師などから「次はご主人と一緒に」と言われ、困惑する方も、まだまだ多いようです。
妊娠には、お互いの協力が必要です。それは夫婦の間に授かる子どものための治療だからなのです。
夫婦の問題に、なかなか他人は助言しにくいものですが、「治療」を前提に考えれば、医師にとっての患者は夫婦なのです。
病院に行きたがらない夫と病院に行きたい妻
不妊原因が女性側にあっても、男性側にあっても、治療に伴うストレスの割合は女性に多くあります。
女性は、赤ちゃんを育てる子宮を持っていることで、より治療を自分のものとして捉えやすいのですが、男性はなかなかそれを実感として持つことは難しいとされています。
通院をする、一緒に診療をする、そのこと自体にプライドを傷つけられたように感じ病院へ行きたがらないご主人もいらっしゃることでしょう。
子どもができないことに対し、まず女性に原因があるのでは?と考えてきた社会の流れもあります。その意識改革とまた男性が行きにくい不妊クリニックの名称を改め、男性も女性も入りやすい不妊治療施設や診療科名があれば much better!!
患者の声
やっと2人でスタートライン
治療を始めて1年、何度もお願いをして、先日初めて2人で診察に行くことができました。主人は、先生から私の状況を聞いて、やっと2人の問題だと分かってくれたようです。今までは私から主人に伝え、たいして関心もないような様子で「へぇ、ふぅん」ばかりで、「本当に子どもが欲しいの?」と聞けば「うん」と答えることは答えるのです。今回、2人で診察へ行った帰りに主人が「今まで悪かったネ」と言ってくれたんです。
これからはスッキリとした気持ちで治療ができそうです。
(宮城県・34歳)
病院に行って欲しいに黙り込む夫
ヒューナーテストの結果は「0」。主治医から精液検査を勧められています。検査結果とこれからのこと、そして「一緒に病院へ行って欲しい」と話しました。
それから何度も病院へと話すのですが、黙り込むばかりで返事がありません。何故そんなにためらうのでしょう。どう話せばいいのでしょう。子どもが欲しいと望むことで、夫婦仲が悪くなるなんて思ってもみませんでした。
(埼玉県・38歳)