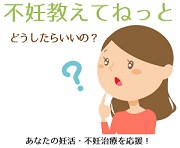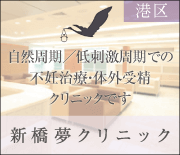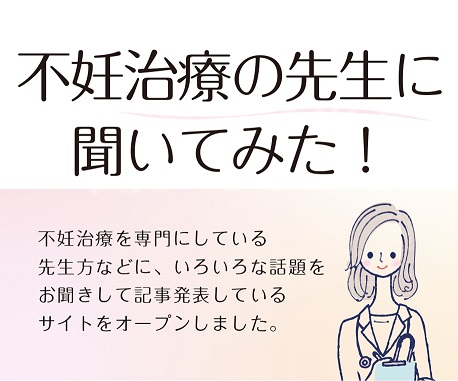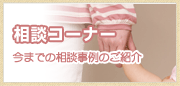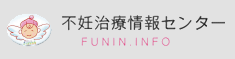助成金の扱い
病院選び
居住地域の助成事業を調べ支払った医療費の一部を取り戻しましょう。
特定不妊治療費助成事業、有効利用していますか?
居住地域で格差のある助成事業
拭えない不公平感はあるにせよ、とにかく利用を…
平成16年4月、厚生労働省は『少子化対策の施策の一環』として、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療費に要する費用の一部を助成することとしました。国と各自治体(各都道府県、政令指定都市、中核市)が支給額を1/2ずつ折半する形でこの事業が始まり、1年が経過しました。
『特定不妊治療』とは、体外受精および顕微授精をいい、施行当初、1年度あたり10万円を限度に(1)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された戸籍上の夫婦、(2)所得制限額650万円(夫婦合算の所得ベース)未満であること、(3)指定された医療機関での治療であることなどの諸条件を満たした夫婦に対し通算2年間支給するものとし、2008年現在、(1)1回の治療につき10万円まで2回を限度に5年間支給、(2)所得制限額は730万円未満と改正されています。(平成19年度から助成対象範囲が設けられています。)
平成17年6月現在、昨年度に検討中、もしくは見送りとした自治体も実施、または実施予定を決め、ほぼ全国で助成が受けられるようになりました。
しかし各自治体の助成事業の概要には差があり、所得制限を設けていない、指定医療機関も県内限定であったり、全国であったり、また独自体制で2年を4年間に延長し支給する自治体もあります。
また市町村独自の不妊治療費助成事業もあり、これは各自治体により助成事業内容に大きな差があります。また特定不妊治療という枠や所得制限枠もなく、特定不妊治療費助成事業との併用も可能な場合もあります。これにより居住する場所によっては、0~百万円近くの差がでてきてしまいます。またプライバシーの問題を含む申請受付場所、申請用紙、相談窓口などは改善されるべきことを多く含んでいます。
特定不妊治療費助成事業の指定施設になっているクリニックとは
各自治体が特定不妊治療費助成事業の指定施設としているのは、社団法人日本産科婦人科学会に、体外受精、顕微授精を実施する登録施設として認められている施設が基本となっています。
日本産婦人科学会では、『ART(生殖補助医療)実施医療施設登録を義務制とし、登録申請を受理された施設がこれを実施する』としています。生殖補助医療を行なう登録施設とは、『具備すべき要件と設備』と『実施医師の要件』を満たしたものが登録されるとしています。
現在、登録施設は700ほどあり、日本国民の人口比率や諸外国から比べると施設数は特出しており、特定不妊治療費助成事業の指定施設となっていても、年間数例しか体外受精を行なっていない、または行なわなかった施設もあるようです。(医師やスタッフの経歴にもよるので批判は避けたいが…)
また通院している施設の受付や待合室に特定不妊治療費助成事業の案内パンフレットやポスターなどがあり、事業内容の簡単な案内ができるスタッフがいることも大切な確認事項のひとつです。
各自治体からの報告では
i-wishでは、特定不妊治療および不妊治療費助成事業の実施状況のアンケートを行ないました。さまざまな課題もあり、当センターは、この事業にどれだけの利用者があり、どれだけ支給されているのかを、不妊相談センターとの連携問題も絡め、情報収集して治療施設へフィードバックすることが、患者利益につながると考えています。特定不妊治療費助成事業が始まって4年になります。まずは厚生労働省がこの事業内容の正確な情報公開をすることが社会の much better!!
患者の声
650万円の壁に…(2006年度に申請)
夫婦2人で働いています。治療費の支払いに困るということは、今のところないのですが、治療費はとても高いものです。不妊治療費助成事業ができ、少しでも次の治療の足しになれば…と申請の手続きを考えました。
あれこれ資料を持って申請へ行きましたが、結果、所得がわずかばかり多く、申請さえできませんでした。フルタイムで夫婦共働き、治療する時間も一生懸命工面しているのに、これではストレスが溜まる一方です。
(東京都・43歳)
どうかお願いです!
結婚して6年、妻は結婚したら早く子どもが欲しいと言っていたのですが、まだ2人でいいと自分のわがままを通してきました。
ところが、子づくりをと頑張りだして1年、未だに妊娠しません。
一昨年、風邪から高熱を出して寝込み、大人になってからの高熱は不妊の原因と聞き、病院へ行ってみようとも思うのですが、自分の検査も怖いのです。子ども好きの妻を思うと、それが原因だとしたら、早くに子づくりをしておくべきだったかと後悔しています。
(愛媛県・32歳)