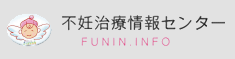病院・クリニック検索はこちら
サイト内検索はこちら
2022年4月から不妊治療が公的医療保険の適用となり、生命保険会社の医療保険(手術給付金、先進医療特約)でお支払いできる場合があります。

【ご注意ください】
記載の給付事例は公的医療保険制度に連動した保障を提供する一般的な医療保険を想定しております。
実際の給付に関しては保険会社ごとに変わりますので必ず保険会社にご確認ください。
また公的保険制度の適用対象の変更により給付内容が変更となる可能性がございますことお含みおきください。
実際の治療内容に関してはお客様ごとに異なりますので、記載の手術名であっても給付金額が異なる場合や請求対象とならない場合も考えられますのでご注意ください。
1.給付金の受け取りイメージ
【加入例】
■医療保険(保障内容が公的保険制度に連動したもの)※1
入院給付金日額:10,000円 手術給付金:入院給付金日額×5倍(入院を伴わない手術の場合)
※1 該当の手術が公的医療保険制度の対象であることが前提のため、健康保険の適用がない場合は支払対象外となります。また、不妊治療の場合、女性の年齢や不妊治療の健康保険適用回数により、健康保険の適用可否が変わりますので、詳細は医療機関にご確認ください。
ケース① 人工授精を1回行った場合
| 治療費用 | |
|---|---|
| 一般不妊治療、管理料 | 750円 |
| 人工授精(1回あたり) | 5,460円 |
| 治療費合計 | 6,210円 |
※別途初診料や検査費用がかかるケースがございます。
| 入院・手術給付金 | |
|---|---|
| 人工授精(手術給付金) | 50,000円 |
| 給付金合計 | 50,000円 |
※<手術給付金・外来>入院日額×5倍
ケース② 顕微受精1回行った場合
| 治療費用 | |
|---|---|
| 採卵(採卵数5個) | 20,400円 |
| 顕微授精(卵子数5個) | 20,400円 |
| <先進医療>ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) | 26,400円 |
| <先進医療>タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 25,300円 |
| 培養(5個培養)※初期胚培養 | 18,000円 |
| 胚盤胞培養(5個) | 6,000円 |
| 凍結保存(2個凍結) | 21,000円 |
| 胚移植 | 36,000円 |
| アシステッドハッチング(AHA) | 3,000円 |
| 治療費合計 | 176,500円 |
※別途初診料や検査費用がかかるケースがございます。
| 入院・手術給付金/先進医療特約給付金 | |
|---|---|
| 採卵術 | 5,000円 |
| 体外受精・顕微授精管理料 | 50,000円 |
| <先進医療>技術料 | 実額給付 |
| <先進医療>技術料 | 実額給付 |
| 受精卵・胚培養管理料 | 50,000円 |
| 胚凍結保存管理料 | 50,000円 |
| 胚移植術 | 50,000円 |
| 給付金合計 | 250,000円 +先進医療の実額 |
※<手術給付金・外来>入院日額×5倍
※上記金額は、不妊治療情報センターにて試算した料金で、実際の料金と異なる場合がございます。
詳細は、医療機関までお問合せ下さい。
※ 「4.先進医療特約の支払い対象となる不妊治療について」を併せてご参照ください。
現在ご加入の内容など不明点があれば、提携保険会社のライフコンサルタントのご紹介が可能です。
新規でご加入を検討されている方も、ご相談可能です。
(既に不妊治療を受けられている方についても、是非ご相談ください。)
※生命保険契約のご検討に際しては、必ず保険会社ごとの「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
2.一般不妊治療と生殖補助医療(体外受精など)の違い
(1)一般不妊治療
| タイミング法 | 排卵のタイミングに合わせて 性交を行うよう指導するもの |
|---|
| 人工授精 | 精液を注入器で直接子宮に注入し、 妊娠を図る技術 |
|---|
(2)生殖補助医療(体外受精など)

3.手術給付金の支払対象となる不妊治療について
| 手術名 | 支払可否(健康保険の適用がない場合は支払対象外) |
|---|---|
| 精巣内精子採取術 | 〇 |
| 人工授精 | 〇 |
| 採卵術 | 〇 |
| 体外受精・顕微授精管理料 | 〇 |
| 受精卵・胚培養管理料 | 〇 |
| 胚凍結保存管理料 | 〇 |
| 胚移植術 | 〇 |
【ご注意ください】
該当の手術が公的医療保険制度の対象であることが前提のため、健康保険の適用がない場合は支払対象外となります。
不妊治療の場合、女性の年齢や過去の治療状況により健康保険の適用可否が異なりますので、健康保険の適用可否に関しての詳細は必ず医療機関へご確認ください。
記載の内容は2025年4月時点での情報をもとに、給付金請求の対象となる代表的な手術名を記載しております。
なお一部保険会社では支払い対象外となるケースもございますので給付の可否については必ず各保険会社にご確認ください。
4.先進医療特約の支払い対象となる不妊治療について
| 先進医療技術名 |
|---|
| 子宮内膜刺激術(SEET法) |
| タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 |
| 子宮内膜擦過術 |
| ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI) |
| 子宮内膜受容能検査1 |
| 子宮内細菌叢検査1 |
| 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術 |
| 二段階胚移植術 |
| 子宮内細菌叢検査2 |
| 子宮内膜受容能検査2 |
| 流死産検体を用いた遺伝子検査 |
| 膜構造を用いた生理学的精子選択術 |
| タクロリムス経口投与療法 |
| 着床前胚異数性検査1 |
| 着床前胚異数性検査2 |
【ご注意ください】
※厚生労働大臣において定められた先進医療が対象です。対象となる先進医療技術は医療機関ごとに定められておりますので厚生労働省ホームページにて、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan03.html
※対象となる先進医療は変動しますので、対象となっていた医療技術、医療機関および適応症等であっても受療された日現在において対象外となる可能性がございます。
現在ご加入の内容など不明点があれば、提携保険会社のライフコンサルタントのご紹介が可能です。
新規でご加入を検討されている方も、ご相談可能です。
(既に不妊治療を受けられている方についても、是非ご相談ください。)
※生命保険契約のご検討に際しては、必ず保険会社ごとの「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。